“子ども主体”の試行錯誤につきあうということ
事例1:キャンプでの初日の食器作り
子どもが合宿場所(旧学校であることが多かった)に到着して、それぞれが段ボールなどで自分の寝場所を確保すると、たいていは探索行動が始まる。
その頃、初参加のスタッフに竹でのお椀・皿・箸といった食器作りを進めておいてもらうといった環境構成を行う。子どもは、大人が何かに一生懸命になっているのを見つけると必ず寄ってくる。そして、尋ねる、「何やってるの?」と。「箸を作ってるんだ」などと答えると、「ふーん」などと言いながら、その様子を見ている。しばらくすると、「ぼくもほしい」とか「私も作りたい」という声になる。そこでたいていの教師はその作り方を教えようとすることになるが、我々は教えない。そして、問題をそのまま子どもに返す、「あなたはどんなふうに作ろうと思うの?」と。すると、見ていた子どもは、「あの竹をのこで切って、ナタで割って、小刀で削る」とその作り方をすでに理解している。そこで、それにつきあうことに。例えば、必要があれば、のこで孟宗竹を切るときに、竹が動かないように押さえるなどを支援する。初めてのこを使う子どもも多く、孟宗竹1本を切断するのにも苦戦することが多い。竹の半分ほどのこが進み、しかし、かなり手こずっている子どもにとっては、さも疲れ切ってしまったかのようなそぶりを見せ、スタッフが「替わってあげようか」と言ってくれるのを待っているかのような状況もある。そのようなとき、もちろんそうしないし、かといって、「あと半分残っているぞ。がんばれ」などといった励ましもしない。「うわあ、もう半分も切れたんだね」とその努力に焦点を当てた“勇気づけ”を行う。そう言われて、気持ちの切り替えができた子どもは再びその課題にチャレンジする。スタッフも、「おお、もう三分の二くらい切れたよ」とか「あともうちょっとだよ」などと、その進歩に焦点を当てて勇気づける。もちろん、切断し終えることができたら、「やったね!」などとその喜びをハイタッチで共有する。
そうして切った竹をナタで割るとき、初めから箸の太さに近い細さで割って、そのまま削っていき、箸先は爪楊枝ほどの細さになり、“失敗した”という感じで、小刀の動きも鈍っている子どもがいることもある。そのようなとき、もちろん、叱ったりはしない。その子どもの残念さにまずは共感する、「あらぁ、うまくいかなかったみたいで残念だったねぇ」などと。ここでは叱られることにならないんだとわかり、かつ、自分の気持ちをわかってもらえることになるんだと気づいた子どもの表情が動き、頷いたり「そうなんだ」と肯定したりする。そうすると、あらためて、子どもに問題を返す、「じゃあ、次はどういうふうに作ろうと思うの?」と。すると、たいていの子どもは、「さっきよりも太く割ってから削る」とすでに解決策を考えていることが多い。「じゃあ、そうしてみようと思うんだね」とその試行錯誤を許されたと思える子どもは、すぐに次に取りかかる。先ほどよりも少し太めに割るということに集中して。
そうして2回目の箸づくりに挑戦し、納得できる作品に満足しながら「できたぁ」と喜ぶ姿を見せてくれる。もちろん、ここでもほめないで、「自分でうまくできてとってもうれしそうだねぇ」と、その達成の喜びに共感する(“勇気づけ”)のである。
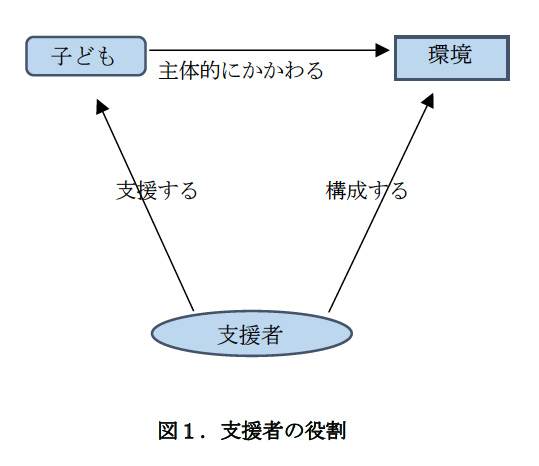
- カテゴリー
- ふれあい合宿&チャレンジ・キャンプ
